| 最終更新日(update) 2023.12.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
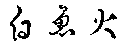
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日(update) 2023.12.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
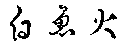
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
| 句会報(H17-18)へ | 句会報(H19-20)へ | ||||||||||
| 句会報(H21-22)へ | 句会報(H23)へ | ||||||||||
| 句会報(H24)へ | 句会報(H25)へ | ||||||||||
| 句会報(H26)へ | 句会報(H27)へ | ||||||||||
| 句会報(H28)へ | 句会報(H29)へ | ||||||||||
| 句会報(H30)へ | 句会報(H31)へ | ||||||||||
| 句会報(R2)へ | 句会報(R3)へ | ||||||||||
| 句会報(R4)へ | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
| 令和5年2月号掲載 句会報 |
|
令和四年栃木白魚火忘年俳句大会 |
| (宇都宮)田所 ハル |
|
|
| 令和5年2月号へ |
|
|
| 小春日和に恵まれ、コロナ感染症の憂さも忘れる良き日。令和四年十二月四日。栃木白魚火忘年俳句大会が、宇都宮市中央生涯学習センターを会場に開催されました。 参加者は二十四名。当季雑詠五句出句、七句選(内特選一句選)として挙行。 開会前にまず写真撮影。なごやかな笑顔を揃え無事終了。 中村國司宇都宮支部長の司会。柴山要作会長のご挨拶。その後句会説明があり句会に入った。 参加者の協力と運営スタッフの淀みない作業で清記・選句を終え、松本光子さん、五十嵐藤重さんの披講、中村國司さんの点盛結果発表と順調に進み、上位入賞一位から五位、飛び賞七位、十位、十五位、二十位、ブービー賞までと、行き届いた心遣いの賞品が授与された。 最後に曙、鳥雲同人の方々の特選句についての講評を頂き、感慨深い思いの締め括りでした。 令和五年白魚火新年俳句大会開催の案内、栃木県白魚火会年間合同句集(第四十三号)発行の通知書を頂き、笑顔と緊張の豊かな一日の忘年俳句大会となりました。そのことをお伝えして、大会報告といたします。 曙・鳥雲同人特選句 星田一草 特選 北窓塞ぐ日光連山見えずなり 大野 静枝 柴山要作 特選 七五三ひとつ日差しに祖父母居て 本倉 裕子 中村國司 特選 マフラーをとる時光るイヤリング 星 揚子 加茂都紀女 特選 枯菊の日の温みごと束ねけり 松本 光子 齋藤 都 特選 落葉踏む誰かと語り合うやうに 星田 一草 星 揚子 特選 七五三ひとつ日差しに祖父母居て 本倉 裕子 松本光子 特選 裸木や句集に余白あるやうに 本倉 裕子 「今日の一句」(二十四名、五十音順) 風邪の背を摩る小さな手に力 秋葉 咲女 落鮎の吐息のやうな泡一つ 阿部 晴江 ラム鍋に馬乳酒の夢大相撲 五十嵐藤重 月命日庭の寒菊携へて 石岡ヒロ子 菊白子朱塗りの椀のお吸物 上松 陽子 霜柱のやうにビル立つ朝まだき 江連 江女 苔もみぢ朽ちかけてをり開祖の碑 大野 静枝 鐘を撞く僧ののけぞる冬の空 加茂都紀女 鯛焼は先づかりかりの尻尾から 熊倉 一彦 点滅の信号うるむ夕しぐれ 齋藤 英子 しぐるるや病歴語る猫にまで 齋藤 都 白菜のキムチ漬け込む姉妹 佐藤 淑子 裾端折り磴百段を七五三 柴山 要作 短日やまづ点したり厨の灯 鷹羽 克子 三國峠上越出会ひの里神楽 田所 ハル 煮凝のまだ四角なり五穀飯 中村 國司 厨女の優しき味方ちやんちやんこ 中村 早苗 顔なしの丸鶏すゑてクリスマス 奈良部美幸 暮早し山に山影重なりて 星 揚子 落葉踏む誰かと語り合うやうに 星田 一草 枯菊の日の温みごと束ねけり 松本 光子 裸木や句集に余白あるやうに 本倉 裕子 山眠る砂利採る音の遠くして 谷田部シツイ 咲き散りて初冬の庭の静かなり 渡辺 加代 |
 |
|
|
|
|
| 令和5年2月号掲載 句会報 |
|
名古屋句会報「俳句講座」開催 |
| 伊藤 達雄 |
|
|
| 令和5年2月号へ |
|
|
| 令和四年十一月二十日の名古屋句会は特別意義のある句会となりました。というのも第二回(平成二十八年)より句会場としている名古屋市中村生涯学習センターから、「俳句の講座を開催されては」とのお誘いにより、募集に応募された方を加えた講座句会としてはじめて開催したからです。私達も、会員を何とか増やそうと対策を模索していたこともあり、よいタイミングとなりました。檜垣会長はじめ全員で三回の講座の内容、進行、パンフレット等を検討し、今回の兼題「冬紅葉」と共にセンター内にポスターとして掲示しました。内容等は別掲のとおりです。 参加登録は会員の熱心な呼びかけもあり、六名と想像以上でした。当日は浜松から鳥雲集選者の渥美絹代先生と渥美尚作さんも駆けつけてくださり、大変盛り上がりました。初参加の方々(一名は急な体調不良により欠席、一名は欠席投句)は人生経験に富まれ、とても素晴らしい句を出されました。渥美先生は一句一句に丁寧な評をなされ、辞書による語句の確認等選句を通じてご教授頂きました。初参加の方々も入選句、秀句、特選句等に選ばれ、名乗りを上げる度に感嘆の声が上がっていました。今回は初参加の方々の両隣に会員が座り、個々の不明な点に対応しました。 銀杏並木の見事な黄葉を見つつ、第一回目の講座は楽しく成功裏に閉じました。初参加の方々からは「こんなに丁寧に教えていただけるとは想像していなかった」「俳句ってすごく楽しいですね」等の感想が寄せられました。渥美先生をはじめとして会員諸氏のご尽力に感謝すると共に、名古屋句会が益々発展していくことを願ってやみません。 一句抄 笹鳴や的を大きくそれたる矢 渥美 絹代 蕎麦の花明治の二階建校舎 渥美 尚作 食パンで消すデッサンや冬雀 檜垣 扁理 ポケットに古きレシート冬はじめ 安藤 春芦 鳥の声聞きつつ竿に柿吊す 伊藤 妙子 冬紅葉賽銭箱にふはり落つ 伊藤 達雄 軒先の鋸の音聞く小春かな 大塚 知子 祖母と二人遠いあの日の日向ぼこ 兼松和加予 膝抱いて障子明かりに聴く法話 後藤 春子 父植ゑし蜜柑たわわに実りけり 白井 幸雄 沢音の幽かにとどく冬桜 野田 美子 仁和寺にまだ残りたる冬紅葉 前田 泰子 一生は五枚の戸籍冬紅葉 牧野 敏信 ふと拾ひ陽に翳したる冬紅葉 前野 砥水 バリトンの流るる窓辺冬紅葉 三宅 玲子 反応なき指紋認証文化の日 吉村 道子 |
 |
|
|
|
|
| 令和5年2月号掲載 句会報 |
|
坑道句会十一月例会報 |
| 榎並 妙子 |
|
|
| 令和5年2月号へ |
|
|
| コロナ収束もままならない昨今ですが、十一月二十八日(月)に五か月ぶりの吟行句会が行われました。皆さんご都合もあり、今回は十三名の会員が集いました。小春の雲一つない青空の下、紅葉が一際映え、まさに吟行日和でした。 参加者は、江戸時代からの面影を残す木綿街道と六百本の桜をはじめとするたくさんの樹木に囲まれ、動物広場、ちびっこ広場や展望台、スポーツ施設、古川句碑などのある平田市民の憩いの場所である愛宕山公園周辺をそれぞれに吟行しました。 木綿街道は、渋塗りの壁や格子戸が冬日を浴びてきらきらと鮮やかでした。門ごとに竹筒に棉の木が飾られ、道行く人を歓迎しています。三百年続く生姜糖屋、酒屋、醤油屋などが並ぶ昔の風情ゆたかな街並をゆっくり歩きました。 出雲地方の木綿は此処に集まり、船で松江など他の地方に運ばれたそうです。こうして話を聞きながら、熱心に吟行されている句友の瞳は輝いています。 愛宕山公園には、世界一大きな兎がいて珍しく、ほかにカンガルーや驢馬、ポニー、山羊、鹿などの動物やいろんな鳥もいて、休日はちびっこを中心に賑わっています。池には鴨が戯れ、グラウンドゴルフの球の音も聞こえてきます。そして、四季折々の樹木の景が美しい句碑が丘は、沢山の人が足を運ばれ、俳句ができない時は、「古川句碑に行く」って良く耳にしました。 吟行の後の句会は、JAしまね平田中央支店会議室。皆さんの素晴らしい作品が投句され、句会は盛り上がりました。残念ながら参加者数は少なかったのですが、熱気にあふれる、楽しい有意義な句会となりました。 渡部美知子特選 深秋の色を背にして古川句碑 荒木千都江 落葉踏み母校へ長き坂登る 三原 白鴉 一輪のもの言ひたげな返り花 荒木千都江 まろき腹つらね白鳥低く翔ぶ 牧野 邦子 山の池さざ波連れて白鳥来 杉原 栄子 荒木千都江特選 晩じるの句碑へ落葉の散り止まず 三原 白鴉 船川のゆるりと流る小六月 井原 栄子 木綿街道川面に映す木守柿 久家 希世 樗の実声良き鳥の一羽来て 三原 白鴉 山眠る師の句碑いよよ鎮もれり 生馬 明子 久家 希世特選 冬うらら園児の声や古川句碑 榎並 妙子 かけだしは昔の名残山眠る 大菅たか子 小春日の赤い格子戸町の蔵 生間 幸美 吟行はおにぎり二つ冬日和 生馬 明子 枇杷の花木綿街道倉の街 大菅たか子 生馬 明子特選 白壁の屋号のうすれ枇杷の花 原 和子 山の池冬空映し日矢映す 杉原 栄子 寒雀枝折れさうに固まりて 持田 伸恵 湖の傍過ぐれば晴るる冬の霧 牧野 邦子 まろき腹つらね白鳥低く翔ぶ 牧野 邦子 牧野 邦子特選 芽水仙すくと伸びたり古川句碑 原 和子 船川のゆるりと流る小六月 井原 栄子 奥津城を囲む石柵竜の玉 三原 白鴉 白鳥の首を自在に羽繕ひ 井原 栄子 白壁の屋号のうすれ枇杷の花 原 和子 当日の高得点句 八点 船川のゆるりと流る小六月 井原 栄子 白壁の屋号のうすれ枇杷の花 原 和子 船川へ白を散らせり枇杷の花 渡部美知子 七点 晩じるの句碑へ落葉の散り止まず 三原 白鴉 樗の実声良き鳥の一羽来て 三原 白鴉 六点 かいつぶり潜る水輪と浮く水輪 荒木千都江 吟行はおにぎり二つ冬日和 生馬 明子 まろき腹つらね白鳥低く翔ぶ 牧野 邦子 当日の一句抄(氏名五十音順) 深秋の色を背にして古川句碑 荒木千都江 一葉落つ追ひかくるごとまた一葉 生馬 明子 小春日の赤い格子戸町の蔵 生間 幸美 船川のゆるりと流る小六月 井原 栄子 青空につんと尖りて冬木の芽 榎並 妙子 枇杷の花木綿街道倉の街 大菅たか子 草の絮ふはりふはりと古川句碑 久家 希世 格子戸の木綿街道冬日差す 杉原 栄子 芽水仙すくと伸びたり古川句碑 原 和子 白魚火誌の表紙の街や新酒の香 福間 弘子 湖の傍過ぐれば晴るる冬の霧 牧野 邦子 晩じるの句碑へ落葉の散り止まず 三原 白鴉 寒雀枝折れさうに固まりて 持田 伸恵 船川へ白を散らせり枇杷の花 渡部美知子 |
 |
 |
|
|
|
|
| 令和5年2月号掲載 句会報 |
|
ひひな会一泊吟行会 |
| 田久保 峰香 |
|
|
| 令和5年2月号へ |
|
|
| 九月二十三日に「西九州新幹線かもめ号」が開業したのを機に「ひひな会」は十月二十七日、二十八日の一泊吟行会を行った。武雄温泉駅から長崎駅までの日本一短い新幹線の旅となった。長崎は唐寺が多く、先ず竜宮城を思わせる朱の楼門の崇福寺と興福寺を訪ねた。境内には旧唐人屋敷門、極彩色の媽祖堂、朱塗の鐘鼓楼等、朱の建物の明るさと時代の重さを感じた。坂の多い寺町通りを後に、現存最古の眼鏡橋へ。小春日和を貪るように橋の多さを見ながらひと時を過ごした。中華街は車の中から見て孔子廟へ。ここは広大な敷地に、孔子の高弟七十二賢人の石像が並んでいて圧巻であり、まるで異国にいるような気分だった。ここまでで吟行を終え、佐賀の嬉野温泉泊となり、宿に着くや早速句会となった。句会の後はゆっくり食事会。お酒も入り楽しいひとときを過ごした。嬉野温泉の美肌の湯で一日の疲れを癒し、久々の一泊旅行となった。 吟行句 梵鐘のかたき錠前枇杷の花 すみれ 唐寺のベンガラ格子紅椿 藤袴冬も咲かせて崇福寺 史都女 大釜の蓋も大きよかじけ猫 仏具店並ぶ寺町冬紅葉 みち女 唐寺の赤き楼門枯蓮 がまずみや寺町通り坂の町 千 波 狛犬の舌出す冬の竜宮門 寺町に多き仏具屋石蕗の花 ひろ女 禅寺の竹の結界冬椿 冬の薔薇オランダ坂の石畳 瑞 枝 大鍋の錆一色や冬の鵙 長崎は坂多き街柳散る 峰 香 茶の花や古井の蓋の真新し |
 |
|
|
|
|
| 令和5年3月号掲載 句会報 |
|
旭川白魚火句会新年句会 |
| (旭川)吉川 紀子 |
|
|
| 令和5年3月号へ |
|
|
| 去る一月十四日(土)、旭川白魚火会の新年句会が市内の「雪の美術館」近くにある「扇松園」において行われました。 コロナ禍もあり、広いお部屋を用意してくださり、アンティークな雪見窓からはライトアップされた日本庭園が見られ、灯籠や庭石、木々達にこんもりと雪が積もった雪景色を見ながらの句会となり、まさに新年句会にふさわしい会場で、皆さん大喜び。この日は、九名の参加で、淺井まこと、ゆう子夫妻の子、文人君も参加してくれ、みんなに笑顔を振りまきながら、駆け回ったり、早知さんと一緒に遊んでくれたり、時々、ママのおっぱいを吸いに来たりと、自由に楽しんでくれました。 句会は、五句出句で、作品は新年らしい句が勢揃い、中でも峯子さんの「初湯の子爪の先までさくら色」が断トツで、まさにこの日の文人君を思わせる句で大盛り上がりでした。 句会後、男性陣はお風呂に入り、女性陣は、おしゃべりタイム。全員揃ったところで、記念写真をとり、宴会に入りました。次々に運ばれる美味しいお料理に舌鼓をうち、和気あいあいの楽しいひと時を過ごしました。最後に平間代表から、今年の札幌大会への参加の呼びかけなどがあり、改めて気の引き締まる新年句会となりました。 平間純一代表 特選 初湯の子爪の先までさくら色 萩原 峯子 褻も晴れも常の身なりや初雀 萩原 峯子 穴釣や湖底に眠る人柱 沼澤 敏美 吉川紀子 特選 化粧塩光らせてゐる睨み鯛 小林さつき 初湯の子爪の先までさくら色 萩原 峯子 元朝や呼吸の音だけ聞こえ来る 淺井まこと 当日の一句(五十音順) 誰も皆子どもであつた初御空 淺井まこと 人日や魚のやうに父子眠る 淺井ゆう子 茶室いま声の弾みし初稽古 今泉 早知 読初のその一冊を選びかね 小林さつき 愛づるもの雪に埋もれてしまひけり 沼澤 敏美 年取や百まで生くるつもりなり 萩原 峯子 一喜一憂箱根駅伝雪籠 平間 純一 明の春稚の主張のトーキック 望月よしよし 連山の雪を染めゆく初茜 吉川 紀子 |
 |
|
|
|
| 令和5年3月号掲載 句会報 |
|
栃木県白魚火会新春俳句大会 |
| 上松 陽子 |
|
|
| 令和5年3月号へ |
|
|
| 正月飾りがちらほらと残る一月八日(日)、宇都宮市中央生涯学習センターで開催された。今回は、句集「膝抱いて」を上梓された星揚子氏の祝賀の時が設けられた。花束、記念品の贈呈後、星田一草、柴山要作、齋藤都各氏から祝辞と星氏の三十七年間にわたる作句活動のエピソードなどが披露された。星氏の謝辞でセレモニーを終了。句会は、二十四名の参加、五句出句、百二十句から十句選(うち二句特選)とし、成績上位者と特選には、賞品が授与された。 役員の特選句と今日の一句は以下の通り。 星田一草 特選 白菜を洗ふ豊かな水の音 秋葉 咲女 少年のピアノの調べ二日かな 齋藤 英子 柴山要作 特選 乳母車押して一家の御慶かな 上松 楊子 年の酒三年分の話して 本倉 裕子 加茂都紀女 特選 初日さす手入れ届きし庭深く 大野 静枝 足音の追ひ越し際の白き息 星 揚子 齋藤 都 特選 連山の白銀光る初景色 齋藤 英子 叶ふまで変はらぬ誓ひ初日の出 中村 早苗 星 揚子 特選 「膝抱いて」の句集を膝に読始 江連 江女 着水の水脈ながながと小白鳥 谷田部シツイ 熊倉一彦 特選 片耳の少しくづれて雪兎 菊池 まゆ 乳母車押して一家の御慶かな 上松 陽子 本倉裕子 特選 嫁求む絵馬うらがへる若日かな 菊池 まゆ 大根を切干にする風を待つ 齋藤 都 秋葉咲女 特選 輪飾のひとつは夫の杖に掛く 江連 江女 足音の追ひ越し際の白き息 星 揚子 阿部晴江 特選 凧揚のびゆんと音立て向き変はる 星 揚子 神殿の崩れのごとき霜柱 中村 國司 大野静枝 特選 元日やいつもの犬の通り過ぐ 本倉 裕子 白菜を洗ふ豊かな水の音 秋葉 咲女 渡辺加代 特選 蒼穹へほのと紅差す冬木の芽 星田 一草 大らかに羽撃の音や初鴉 秋葉 咲女 中村國司 特選 やあやあと名乗り上げたる初鴉 星 揚子 大根を切干にする風を待つ 齋藤 都 松本光子 特選 凧揚のびゆんと音立て向き変はる 星 揚子 近づきて見慣れぬ形初筑波 本倉 裕子 当日の一句(五十音順) 白菜を洗ふ豊かな水の音 秋葉 咲女 面取れば朝日差し入る初神楽 阿部 晴江 若水の含む一口甘さあり 石岡ヒロ子 乳母車押して一家の御慶かな 上松 陽子 輪飾のひとつは夫の杖に掛く 江連 江女 七草のさだかならねど七日粥 大野 静枝 真青なる空賜りし初詣 加茂都紀女 嫁求む絵馬うらがへる若日かな 菊池 まゆ どかどかと子らの足音福寿草 熊倉 一彦 数へ日の子は滑り台きりもなし 齋藤 英子 小鋏に鈴つけ直す寒の入 齋藤 都 氏神の鳥居に磴に淑気満つ 佐藤 淑子 白鳥とふ無垢なる百花遠筑波 柴山 要作 冬夕焼バックミラーの枠の中 杉山 和美 故郷の山河あまねく初明り 鷹羽 克子 年用意済んで一献そばの膳 田所 ハル 円仁の見し白鳥の嬥歌かな 中村 國司 叶ふまで変はらぬ誓ひ初日の出 中村 早苗 凧揚のびゆんと音立て向き変はる 星 揚子 蒼穹へほのと紅差す冬木の芽 星田 一草 神牛のおん身つややか初日影 松本 光子 近づきて見慣れぬ形初筑波 本倉 裕子 着水の水脈ながながと小白鳥 谷田部シツイ 淑気満つ天狗の里の大鳥居 渡辺 加代 |
 |
|
|
|
|
| 令和5年4月号掲載 句会報 |
|
坑道句会 二月例会報 |
| 三原 白鴉 |
|
|
| 令和5年4月号へ |
|
|
| 令和五年二月二十七日(月)、出雲市十六島町、北浜町周辺を吟行する坑道句会二月例会を開催しました。 島根半島は、「出雲國風土記」において、 「紫菜(のり)が生える。紫菜は楯縫郡が最も優れている。」とあるように、奈良時代から海苔の産地として知られており、なかでも楯縫郡(旧平田市の辺り)の海苔、就中「十六島海苔」は品質が高く、古くから朝廷、幕府にも献上され、茶人大名として有名な松江藩七代藩主松平不昧は、十六島海苔で作った裃を着けて江戸城に登城し、それを千切って居並ぶ大名にふるまい驚かせたり、また出雲大社の御師が御札と共に十六島海苔を配り、信仰普及に当たったことなどから、全国的に名が通った産物となり、歳時記にも「十六島海苔」が季語として載っています。
当日は風もなく海も穏やかで絶好の採取日和ではありましたが、海苔採取期間の最末期ではるか岬の先端部だけで摘み取りが行われており、残念ながら採取の光景は身近に見学できませんでした。 加工場では、海苔島で摘まれたばかりの海苔、かもじ海苔加工用の九十センチ×六十センチ大の大きい巻簀や採取期後半に加工するA四を一回り大きくした大きさの漉簀と漉き桁、簀に貼った海苔を乾燥させるための竹幹の棚、乾燥途中の海苔簀などを峯夫さんの説明を聞きながらじっくりと見学することができました。
当日の句会参加者は、荒天による日程変更の影響などもあって、十二名と前回に続き少人数となってしまったものの、加工場に立てかけられた海苔簀に乾きゆく海苔の様子や漁港の水揚げの様子などを描いた佳句が沢山発表され、熱気に溢れた充実した句会となりました。 最後に、幹事の原和子さんから、この三年はコロナウイルスのため、満足に開催できない状況が続いたが、ようやくコロナウイルス感染状況も落ち着きを見せ、感染症法上の取り扱いも五月から第五類となり、活動しやすくなるので、新年度からは以前のように定期的に開催していきたい旨が述べられ、句会を終わりました。
荒木 千都江特選 潮風に干さるる海苔簀香を放つ 井原 栄子 水平線丸く膨らむ春の海 井原 栄子 漉き紙の如く干さるる海苔簀かな 福間 弘子 海苔小屋を抜くる潮風十六島 原 和子 身を反らし海風に海苔乾きけり 三原 白鴉 久家 希世特選 浦人の竹筒に汲む春の潮 三原 白鴉 沖船のしきりに光る春の海 荒木千都江 春潮にゆらぐ磯菜のあをあをと 牧野 邦子 漉き紙の如く干さるる海苔簀かな 福間 弘子 東風吹くや帰る漁船の招き旗 榎並 妙子 生馬 明子特選 宝石のやうな玻璃片磯遊 三原 白鴉 海風のやさしき音や木の芽晴 榎並 妙子 海見ゆる畑を小さく耕せる 牧野 邦子 一湾を吹き来る風や海苔乾く 牧野 邦子 水平線丸く膨らむ春の海 井原 栄子 三原 白鴉特選 立て掛けて海苔簀百枚透きとほる 原 和子 一湾を吹き来る風や海苔乾く 牧野 邦子 海光のとどく学舎木々芽吹く 原 和子 海透けてさゆらぐ若布見えにけり 井原 栄子 海苔の岩打ちては湾の波あそぶ 荒木千都江 牧野 邦子特選 立て掛けて海苔簀百枚透きとほる 原 和子 ひたすらに海を眺めて二月尽 榎並 妙子 宝石のやうな玻璃片磯遊 三原 白鴉 海光のとどく学舎木々芽吹く 原 和子 早春の海風に身を晒しけり 荒木千都江 当日の高得点句 十点 立て掛けて海苔簀百枚透きとほる 原 和子 八点 水平線丸く膨らむ春の海 井原 栄子 漉き紙の如く干さるる海苔簀かな 福間 弘子 六点 早春の海風に身を晒しけり 荒木千都江 潮風に干さるる海苔簀香を放つ 井原 栄子 ひたすらに海を眺めて二月尽 榎並 妙子 海風のやさしき音や木の芽晴 榎並 妙子 海光のとどく学舎木々芽吹く 原 和子 河下港を透かしてのぞむ海苔簀かな 山本 絹子 当日の一句抄(氏名五十音順) 早春の海風に身を晒しけり 荒木千都江 春の潮テトラポッドを歌はせて 生馬 明子 水平線丸く膨らむ春の海 井原 栄子 海風のやさしき音や木の芽晴 榎並 妙子 海苔摘みも今日で終りと惜しむ声 大菅たか子 澪標流れ和布の光りけり 久家 希世 海底の砂にひかりの届き春 小澤 哲世 トロ箱に並ぶ津走の海の色 原 和子 漉き紙の如く干さるる海苔簀かな 福間 弘子 一湾を吹き来る風や海苔乾く 牧野 邦子 海に裾落とし岬の山笑ふ 三原 白鴉 海苔掛くる竹の節々なめらかに 山本 絹子 |
|
|
|
| 令和5年5月号掲載 句会報 |
|
令和五年度白魚火全国大会吟行地(札幌市)案内 |
| (札幌) 高田 喜代 |
|
|
| 令和5年5月号へ |
|
|
|
○大通公園
西十三丁目には「札幌資料館」があります。ここは、札幌控訴院として建てられたもので、現存する控訴院は、ここ札幌と名古屋だけだそうです。
○時計台 旧札幌農学校演武場
○北海道庁旧本庁舎(赤レンガ庁舎)
また、道庁の西側に国内最初の近代植物園として明治十九年開園の「北大植物園」があります。敷地は約十三ヘクタール、原生林、灌木園、季節の草木や花、博物館などがあり、園内散策ルートとして四十五分と九十分のコースが園内マップに載っています。
○北大キャンパス ○中島公園
中島公園の紅葉は十月中旬~下旬が見頃で、特に公園入口の銀杏黄葉は一見の価値ありです。園内には「菖蒲池」があり、紅葉と池、まさに句材の宝庫です。 ○北海道神宮 ○さっぽろ羊ケ丘展望台
羊が牧草を食む牧歌的風景の中、クラーク博士の像と一緒のポーズで記念撮影はいかがですか。
○狸小路商店街・札幌二条市場
以上、札幌市内を中心にご紹介をしました。何といっても観光名所盛りだくさんの北海道。 |
|
|
|
|
| 令和5年5月号掲載 句会報 |
|
中村公春句集『菊の酒』上梓祝賀句会 |
| 小林 さつき |
|
|
| 令和5年5月号へ |
|
|
|
令和五年一月、公春さんの句集『菊の酒』が上梓されました。旭川白魚火一同でこれをお祝いをしようと、三月十一日祝賀句会を開催しました。会場は、公春さんが幼い頃からお世話になったという旅館扇松園。 祝賀会の前にまずは祝賀句会です。みなさんやはりお祝いの句が目立ちました。 参加者の一句 句会が終わり、祝賀会となりました。句会からお祝いの花籠を贈呈し、記念撮影。そして、句集『菊の酒』の中から一人一句ずつ選んで感想を述べ合うことに。聞いている公春さんは面はゆいようでしたが、もうみんな言いたいことがたくさんあって、付箋だらけの句集を片手に大盛り上がりでした。 以下は、出席各人の一句鑑賞要約です。 句集『菊の酒』より一句鑑賞 ○平間 純一 祝賀会の頃には最年少参加者の文人君もおしゃべりしたり歌ったりして参加してくれ、公春さんは幼馴染の扇松園の女将さんとも思い出話が尽きないようで、楽しい、うれしい会になったことを本当に喜んでいます。
|
|
|
|
| 令和5年5月号掲載 句会報 |
|
内田景子さんおめでとう会 |
| 篠原 凉子 |
|
|
| 令和5年5月号へ |
|
|
|
内田景子さんの白魚火賞受賞のお祝いに日本の滝百選に選ばれた、唐津市相知町の見帰りの滝近くの河津桜など滝周辺へ吟行しました。河津桜は、満開で身も心も引き込まれそうな美しさでした。又はらはらと舞う花びらのなんとも言えない風情に心癒されました。水面を流れる花筏にも見入りました。 吟行句
|
|
|
|
|
| 令和5年6月号掲載 句会報 |
|
古刹峯寺を訪ねて |
| 大東笹百合句会 原 みさ |
|
|
| 令和5年6月号へ |
|
|
|
今年は桜の開花宣言が殊の外早く、ここ雲南の名所が桜一色に染まったのを機に三年振りに吟行句会を計画した。 当日の作品
|
|
|
|
| 令和5年7月号掲載 句会報 |
|
栃木県白魚火総会 俳句大会報告 |
| 渡辺 加代 |
|
|
| 令和5年7月号へ |
|
|
|
令和五年度の栃木県白魚火総会、俳句大会が四月九日(日)宇都宮西生涯学習センターにおいて二十四名出席のもと開催されました。まず、総会に先立ち、髙島文江さんが令和五年三月二十八日にお亡くなりになりましたので、全員で黙禱を致しました。その後、柴山会長より挨拶があり、会員を増やしていきたい旨の話がありました。続いて令和四年度行事報告、決算報告・監査報告、令和五年度行事予定案、予算案、役員・支部構成案等の審議承認があり、俳句大会に移りました。
|
|
|
|
|
| 令和5年7月号掲載 句会報 |
|
令和五年度群馬白魚火会総会及び句会 |
| 遠坂 耕筰 |
|
|
| 令和5年7月号へ |
|
|
|
令和五年四月二十七日、中之条町に於いて今年度の総会および句会が行われました。群馬白魚火会四五名のうち一九名の参加です。
|
|
|
|
| 令和5年7月号掲載 句会報 |
|
浜松白魚火会第二十五回総会、俳句大会及び |
| 大澄 滋世 |
|
|
| 令和5年7月号へ |
|
|
|
令和五年四月二十三日(日)、ホテルクラウンパレス四階「芙蓉の間」に於いて、会員七十余名と来賓に白魚火主宰白岩敏秀先生、白魚火編集長補佐三原白鴉先生、浜松白魚火会顧問黒崎治夫先生をお迎えして、浜松白魚火会第二十五回総会、俳句大会及び浜松白魚火会発足三十五周年記念祝賀会が開催されました。
続いて、各賞の受賞者の紹介と表彰式が行われ、みづうみ賞の浅井勝子さん、同秀作賞の山田眞二さん、同奨励賞の青木いく代さん、大澄滋世さん、鳥雲同人に昇格の渥美尚作さん、坂田吉康さんに花束が贈呈され、受賞者等を代表して浅井勝子さんから謝辞が述べられました。
総会及び俳句大会に引き続き、同日午後五時から同ホテル四階「芙蓉の間」に於いて、浜松白魚火会発足三十五周年記念祝賀会が開催されました。
|
|
|
|
|
| 令和5年7月号掲載 句会報 |
|
坑道句会四月例会報 |
| 井原 栄子 |
|
|
| 令和5年7月号へ |
|
|
|
令和五年四月二十三日(日)、出雲市小境町にある一畑薬師を吟行する坑道句会四月例会が開催されました。
渡部美知子 特選
当日の高得点句
|
|
|
|
| 令和5年7月号掲載 句会報 |
|
団栗の会 春の吟行 |
| 大隈ひろみ |
|
|
| 令和5年7月号へ |
|
|
|
令和五年四月六日、団栗の会春の吟行句会を行いました。吟行場所は江田島市沖美町です。美しいビーチがいくつもある、大変風光明媚な沖美町ですが、明治時代に築造された砲台が三か所残っている地域でもあります。
|
|
|
|
|
| 令和5年7月号掲載 句会報 |
|
東広島白魚火水曜句会吟行 |
| 吉田 美鈴 |
|
|
| 令和5年7月号へ |
|
|
|
コロナ禍が大分下火になって来たため長い間中止していた吟行を四月二十六日に行った。
渡邉春枝 選
|
|
|
|
| 令和5年8月号掲載 句会報 |
|
第五回白魚火俳句鍛錬会報告 |
| 幹事 中村國司、檜林弘一 |
|
|
| 令和5年8月号へ |
|
|
|
本札幌鍛錬会の企画は、コロナ禍により丸三年間のブランクを余儀なくされたが、ようやく再開することができた。言わばリベンジ開催である。今回の参加者は三年前の道内応募者を対象としたので、会誌での公募はしなかったことをご了解願いたい。初夏を迎えた札幌にて、参加者皆さんの活気が溢れ、まさに夏めく札幌の鍛錬会となった。 一 開催概要
三 句会・吟行会
一人一句抄 (主宰以下は地区別順)
・B班 発表者 平間純一 |
|
|
|
|
| 令和5年8月号掲載 句会報 |
|
令和五年度栃木白魚火第一回鍛錬吟行会 |
| 星 揚子 |
|
|
| 令和5年8月号へ |
|
|
|
六月十一日(日)、栃木市、いわゆる「蔵の街栃木」の鍛錬吟行会が行われた。昨年、夏季俳句大会吟行会が二年七か月振りに実施されたが、今年度は以前のように名称を「鍛錬吟行会」に戻し、出句数も鍛錬に見合った内容の五句から七句に変更した。参加者は十七名で昨年より若干少なかったが、当初の申し込みは二十一名だったので、ほぼ例年通り。
|
|
|
|
| 令和5年8月号掲載 句会報 |
|
実桜句会総会・吟行報告 |
| (札幌)佐藤 琴美 |
|
|
| 令和5年8月号へ |
|
|
|
リラ冷えの六月四日~五日昨年同様札幌北二条クラブに於いて実桜句会総会・吟行会が行われました。
|
|
|
|
|
| 令和5年8月号掲載 句会報 |
|
静岡白魚火総会記 |
| 大石 初代 |
|
|
| 令和5年8月号へ |
|
|
|
夏も近づく八十八夜、茶処の牧之原台地では一番茶の刈り取りも終わり、里では田植が始まっています。五月十四日(日)令和五年度静岡白魚火総会、俳句大会が開催されました。当日は、あいにくの雨にも拘わらず二十二名の参加をいただきました。
|
|
|
|
| 令和5年8月号掲載 句会報 |
|
令和五年度浜松白魚火会吟行記 |
| 佐藤 升子 |
|
|
| 令和5年8月号へ |
|
|
|
五月二十七日(土)、浜松白魚火会では恒例の吟行会を開催しました。今年の吟行地は牧之原市の大鐘家、静岡空港、石雲院です。参加者は五十九名。浜松市内の二箇所で集合、二台の貸切りバスにて第一の吟行地である大鐘家へ向け、七時三十分に出発しました。
次の吟行地、静岡空港にはバスが横付けされ、ここからは自由行動になります。飛行場を眺望するには二箇所。一つは空港ターミナルビル三階の展望デッキ、ここで今日初めての富士山を見ることができました。もう一つは石雲院展望デッキ、ここは滑走路に最も近い施設で飛行機の離発着を間近に見る事ができます。石雲院へはここから山道を徒歩で数分、総けやきの八脚門の山門に出ます。山門、総門、参道の丁石、本堂の龍門の滝の彫刻が見所で市の指定文化財になっている曹洞宗の古刹です。
村上 尚子 特選
|
|
|
|
|
| 令和5年8月号掲載 句会報 |
|
『忙中閑あり』の吟行句会 |
| (北見)金田野歩女 |
|
|
| 令和5年8月号へ |
|
|
|
新型コロナウイルス禍により、二回延期になっている白魚火全国俳句大会札幌大会が十月に開かれる運びとなり、去る五月二十二日午後、行事部の皆さんと地元会員の打ち合わせが行われました。地元からは、札幌十名、苫小牧三名、旭川・北見各一名が札幌に集いました。行事部からの説明を受け、それぞれの担当が決まっていくと、愈々との想いも高まり、全国の皆様を温かくお迎えしようと心を一つに致しました。
吟行句会参加者当日の一句
|
|
|
|
| 令和5年9月号掲載 句会報 |
|
群馬白魚火会村上鬼城記念館・洞窟観音・徳明園吟行 |
| 天野 萌尖 |
|
|
| 令和5年9月号へ |
|
|
|
令和五年六月二十三日、高崎市村上鬼城記念館、洞窟観音、徳明園へ吟行句会を行いました。前日までの梅雨空も梅雨晴れとなり、十二名にて吟行を楽しみました。
|
|
|
|
|
| 令和5年9月号掲載 句会報 |
|
自然と触れ合い歴史に思いを馳せる |
| 生馬 明子 |
|
|
| 令和5年9月号へ |
|
|
|
令和五年六月二十六日(月)降りしきる雨の中、安食彰彦先生ご出席の下、出雲市斐川町神庭の荒神谷史跡公園への吟行句会を行いました。雨の影響もあって参加者は十四名に止まりましたが、一番の見頃を迎えた古代蓮や睡蓮、沙羅、紫陽花などの花が咲き、赤米の植えられた棚田、そして出土した三百五十八本の銅剣、十六本の銅矛、六個の銅鐸のレプリカが発掘時そのままに置かれた史跡などを巡りました。
観光、吟行地として多くの人が集うのは「蓮の花が咲く頃」ですが、余り人の訪れない真夏や真冬に一人で訪れるのも一興と思います。
|
|
|
|
| 令和5年9月号掲載 句会報 |
|
「石照庭園」吟行記 |
| りんどう句会 妹尾 福子 |
|
|
| 令和5年9月号へ |
|
|
|
六月三日(土)、雲南市木次町平田にある「石照庭園」を訪れ、吟行句会を行いました。
当日の作品(各二句)
|
|
|
|
|
| 令和5年11月号掲載 句会報 |
|
二〇二三年夏の坑道句会報 |
| 荒木 千都江 |
|
|
| 令和5年11月号へ |
|
|
|
八月二十八日(月)隔月に実施している坑道句会を行いました。当日は、全国的な猛暑日だったのですが、出雲でも熱中症警戒アラートが発令され、外出はなるべく避ける、こまめに水分を補給するなど報道がなされていました。その中で、今回は句会場に予定していたJAしまね北浜店会議室が使えなくなり、急遽平田中央支店会議室に変更になったこともあって、計画していた十六島方面への吟行が難しい方が出てきたため、自由吟行に変更となり、猛暑も考慮して無理のないよう持ち出し句も可とすることとなりました。
安食 彰彦特選 順不同(以下同じ)
|
|
|
|
| 令和5年12月号掲載 句会報 |
|
令和五年度栃木白魚火第二回鍛錬吟行会 |
| 松本 光子 |
|
|
| 令和5年12月号へ |
|
|
|
十月一日(日)さくら市に於いて二回目の鍛錬吟行会が行われた。当日は小雨の中二十名が奥州街道の氏家宿(現さくら市)の西導寺に集合。
|
|
|
|
|
無断転載を禁じます |