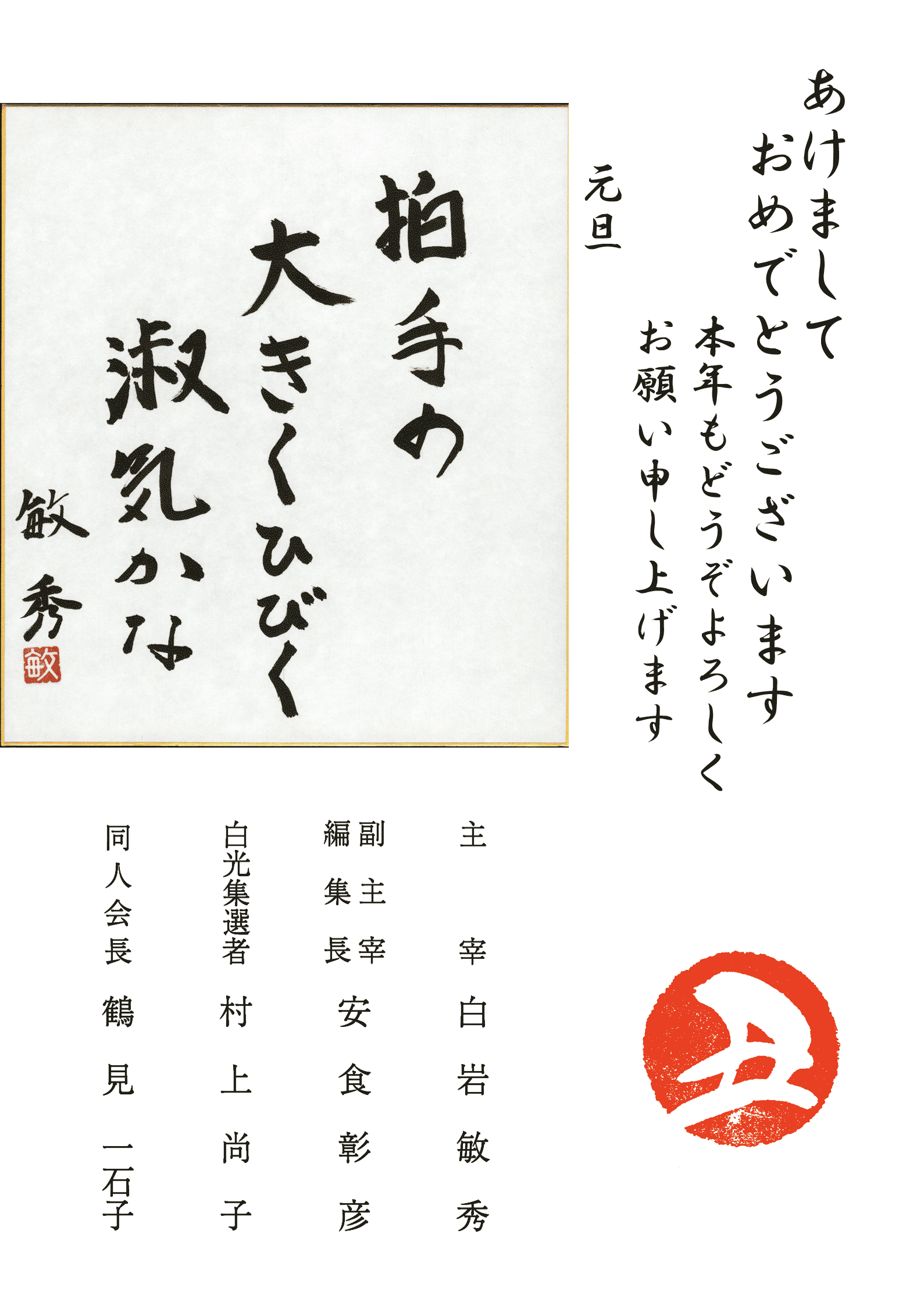|
花野 (静岡)鈴木 三都夫
小鳥啼く人形塚へ惜しみなく
山城の里へ響ける威銃
鵙高音天に最も近くゐて
萩こぼし零しつせせる蜆蝶
駈けて来る子等コスモスの風の中
次の雲までの短き良夜かな
と見かう見しばし花野を去り難し
俳句てふ杖と二人の花野かな
小春 (出雲)安食 彰彦
小春日や飛行雲ひく一穢あり
旅伏嶺に雲かかれども小春空
小春日や吾が影やはり杖を持つ
小六月絵皿筆持つ老爺かな
お誘ひの携帯の鳴る小六月
寂声の軍歌聞こゆる小六月
小春日や出雲阿国の墓に列
小春日やなに啄むか雀二羽
レモン浮く (浜松)村上 尚子
水神の祠小さし稲の波
客待ちの舟を入江に月を待つ
回廊にをり月光に足濡らす
後の月肘やはらかく筆を取る
信濃柿一茶の空を囃しけり
窯出しの壺の一列秋の風
萩焼の壺に投げ入れ女郎花
長くなる話紅茶にレモン浮く
貫頭衣 (唐津)小浜 史都女
秋日濃しからむし生地の貫頭衣
とろとろに冬瓜炊いて半寿過ぐ
貝割菜夜はきらきらと露宿す
烏瓜たぐりしあの日あの日かな
七人の敵健在や天高し
文机にからたちの実と電子辞書
藻の花のつぶやいてゐる神無月
一穢なき遺跡の空や返り花
寒雷 (宇都宮)鶴見 一石子
大根煮る大釜滾る櫂の棹
水枯れて瀬に七宝の石顕は
寒牡丹見て太鼓橋渉りけり
道の駅囲む冬芽の大いなる
寒雷や殺生石に黒き雲
百疊の天狩の宿の隙間風
緋の衣着し僧正や茶の咲ける
夜をこめてリハビリの年虎落笛
冬ざくら (東広島)渡邉 春枝
石段の上も石段紅葉燃ゆ
深秋の老舗の本屋閉店す
長き夜のルーペに捜す旧漢字
文化の日かしこで結ぶ長き文
立冬の再放送のサスペンス
夕日受け鴨一斉に動きだす
よちよちの幼の歩行落葉舞ふ
冬ざくら一輪にして詩の心
鳥渡る (浜松)渥美 絹代
鳥渡る草焚く煙の目にしみて
望の月たてしばかりの畝照らす
烏瓜しばらく土間に吊しおく
貝殻を踏みゆく音や秋夕焼
鳥の影よぎり運動会終はる
渦をなす魚影や鵯のよく鳴きて
風止みて闇濃くなりぬ濁り酒
秋惜しむ河原に鳶の笛聞きて
牡鹿 (北見)金田 野歩女
霧ごめの尾灯頼りの峠越え
筆柿を剥く離れ住む子をふつと
団栗や園児の列の伸び縮み
小雨降る峠の草の錦美し
アングルを低くして撮る珊瑚草
森深し牡鹿あらはれさうな闇
落葉掻く名刹の庭午後も掻く
生命輝く玫瑰の返り花
|
佳きたより (東京)寺澤 朝子
をとこへし活けて火襷あざやかに
コスモスや風と抜けゆく路地ひとつ
織り成せる紫式部白式部
学校に隣る公園小鳥来る
上げ潮に釣瓶落しの隅田川
秋深し朝餉の卵こつと割り
久に観るシネマは「慕情」秋逝けり
神在の国よりとどく佳きたより
満天星紅葉 (旭川)平間 純一
黒葡萄このひと房を届けたし
尾を叩くつなぎとんぼの潦
甌穴は魔神の足跡山粧ふ
一の鳥居くぐり神苑照紅葉
紅葉かつ散りて殉役軍馬之碑
待たさるることも治療や秋惜しむ
一山の満天星紅葉燃えつくす
袴着や着付け正され神妙に
釣瓶落し(宇都宮)星田 一草
石を飛ぶ鶺鴒石へしなやかに
白鷺の歩む刈田の広さかな
蟷螂の思案してゐる首傾げ
榠樝の実疵は目鼻のごとくあり
星ひとつ生まるる釣瓶落しかな
朝寒や名なき墓石の平家塚
なにするも一人や秋の咳ひとつ
秋の水石それぞれに老いゆけり
秋深し (栃木)柴山 要作
宿坊の朝餉いろどる秋茄子
朝寒の玉砂利踏んで巫女出仕
稲刈つて筑波の双耳いよよ美し
メトロノームめく牛の尾や昼の虫
せせらぎのおしやべり嬉々と秋うらら
秋の旅少し色さす眼鏡かけ
露けしや殺生石も千佛も
秋深し小草に身をば沈むる蝶
朴一葉 (群馬)篠原 庄治
釣舟草一漕揺らす早瀬かな
天に燃え地に朽ち果てし曼珠沙華
秋茄子の味噌汁あれば菜いらず
松手入れ肩より匂ふ貼り薬
草紅葉石と化したる風化仏
山霧を止めて白し蕎麦の花
梯子下り暫し思案の松手入
錐揉みに朴の一葉の舞ひ落つる
二百二十日 (浜松)弓場 忠義
誰もゐぬ田に煙立つ秋の暮
妻とゐてたがひの夜長もて余す
一輪車伏せしまま置く刈田かな
にはとりの長鳴き二百二十日かな
黄落の途切れし辻に人を待つ
姫様の襟元正す菊師かな
霜月の土柔らかく鋤きにけり
初しぐれ露地に関守石を置く
旅心 (東広島)奥田 積
自給米に稲架組まれゆく母屋前
満開の十月桜偉人の碑
鳥渡る天地一つに佐田岬
旅に会ふ旅の親切秋夕焼
笑ひ声林檎切る音齧る音
地滑りの山を四方に花野径
影を引き夕日落ちくる赤まんま
目を閉ぢて聞こゆる音や秋深し
福耳 (出雲)渡部 美知子
神官の衣擦れ秋の日のこぼれ
乗り合はす人は福耳秋うらら
色変へぬ松日沉の朱の宮居
(※日沉宮=日御碕神社)
秋刀魚焼く火の高ぶりの美しく
和だんすに眠る道行十三夜
鳴り止まぬ喝采のごと銀杏散る
一望のうす墨色や冬近し
ひたひたと神の足音冬に入る
|