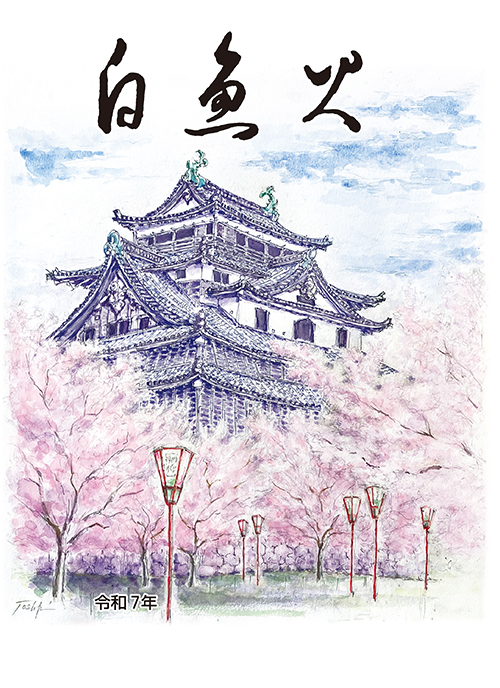| 最終更新日(Update)'25.11.04 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
| (アンダーライン文字列をクリックするとその項目にジャンプします。) |
|
|
|
|
|
山羽 法子、妹尾 福子 |
|
|
|
|
|
広谷 和文、浅井 勝子 |
|
|
|
|
|
|
| 季節の一句 |
|
|
| (松江)小村 絹代 |
|
|
|
心地よき出雲訛やぬくめ酒 荻原 富江
枯菊焚く明治の母の文も焚く 陶山 京子
香一本くゆらせ秋の声をきく 小林 さつき
|
|
|
|
|
|
| 曙 集 | |
| 〔無鑑査同人 作品〕 | |
|
|
|
|
門火焚く (出雲)安食 彰彦 |
秋高し (栃木)柴山 要作 |
|
|
|