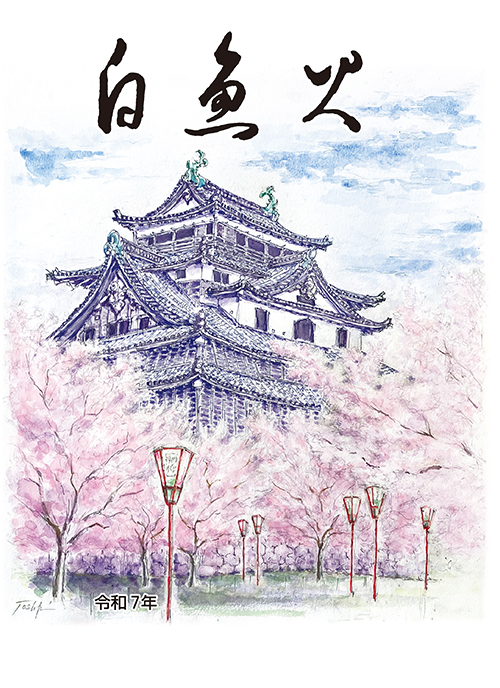| 最終更新日(Update)'25.10.03 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
| (アンダーライン文字列をクリックするとその項目にジャンプします。) |
|
|
|
|
|
小林 さつき、野田 美子 |
|
|
|
青木 いく代、高橋 茂子 |
|
|
|
|
|
|
| 季節の一句 |
|
|
| (浜松)鈴木 誠 |
|
|
|
百歳の葬列長し秋高し 深井 サエ子
秋の蚊や飛び立てぬ程血を吸ひて 伊藤 妙子
兄ちやんの彼女も入れて栗ごはん 小嶋 都志子
|
|
|
|
|
|
| 曙 集 | |
| 〔無鑑査同人 作品〕 | |
|
|
|
|
海の日 (出雲)安食 彰彦 |
晩夏 (栃木)柴山 要作 |
|
|
|