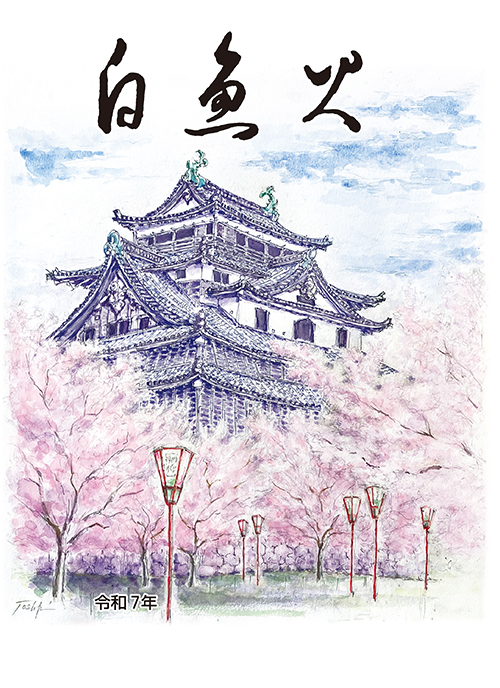| 最終更新日(Update)'25.07.01 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
| (アンダーライン文字列をクリックするとその項目にジャンプします。) |
|
|
|
|
|
工藤 智子、斉藤 妙子 |
|
|
|
|
|
安部 育子、滝口 初枝 |
|
|
|
|
|
|
| 季節の一句 |
|
|
| (旭川)小林 さつき |
|
|
|
夢ひとつ叶ひ四葩を飾る朝 工藤 智子
バイク遂に原付となり遠花火 川上 征夫
梅雨入や塩をひと振り糠床へ 柴田 まさ江
|
|
|
|
|
|
| 曙 集 | |
| 〔無鑑査同人 作品〕 | |
|
|
|
|
古川の忌 (出雲)安食 彰彦 |
初音 (群馬)篠原 庄治 |
|
|
|