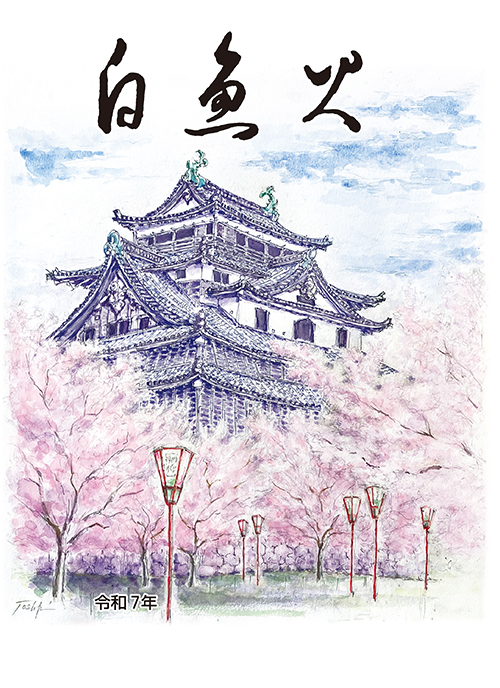|
日脚伸ぶ (出雲)安食 彰彦
風邪声の電話の主は風邪の神
講堂のあのしはぶきは父の咳
蠟梅の明るくいよよ透きとほる
咲きみつる蠟梅の空晴れわたる
日脚伸ぶ厨の仕事あとにして
日脚伸ぶ忘れ物して舞ひ戻り
日脚伸ぶひとりぽつちの下校の子
下駄箱のどこも空つぽ日脚伸ぶ
初写真 (浜松)村上 尚子
初写真誰かがきつとそつぽ向く
初旅といふほどもなき駅に下る
初富士の裾野を洗ふ波がしら
行きずりの神に礼して三日かな
まゆ玉の人の気配にゆれてをり
着ぶくれて電車の席をゆづり合ふ
酒飲んで田遊の牛声を出す
寒鯉に遅れて水の動きけり
冬の芹 (浜松)渥美 絹代
減りたる荷並べかへては飾売
目薬師の井戸に花つけ冬の芹
松の内雀にすこし米を撒く
鳥声の絶えざる屋敷小正月
編みかけの毛糸やくわんの鳴つてをり
寒の梅ほどけて夫の誕生日
塗椀に金の松の絵雪催
きさらぎの北山杉の床柱
譜面台 (唐津)小浜 史都女
白障子天山見るに立ちあがり
百花園冬芽ばかりを巡りけり
譜面台立ててたたみて春もそこ
水仙に決められし丈ありにけり
雪どけの天山日々に痩せてきし
雲にこころ水にこころや春動く
風船に八十の息満たしけり
貝寄やももいろの貝拾ひたる
毛の国 (宇都宮)中村 國司
大根干す総木づくりの峡の宿
あれやこれ縛り直され冬の菊
カーテンのふと艶めける初茜
音あれば耳のかたむき七日粥
普陀洛の涯やうすづく寒の月
寒紅をちらりチラ見や男の子
大鬼怒の夜明け仄かに鴨の声
毛の国の春はすぐそこ徘徊る
雛まつり (東広島)渡邉 春枝
庭に雪つもりて今日は雛祭
三姉妹そろつて座る雛の前
雛段に玩具も並べ笑ひ顔
雛段を背伸びして観る三姉妹
雛の豆高くふりまく佛の間
雛の豆一粒づつに母の味
雛料理少し甘めに皿に盛る
児と同じ高さより観る雛の段
浜風 (北見)金田 野歩女
浜風の頰刺す中を鱈干しぬ
煤逃の夫に頼む小買物
初日の出湖分かつ光の緒
くつきりと晴れて盆地の淑気かな
初詣箒目清しき磴踏みて
取つて置きの椀に盛りたる雑煮かな
初星や子の夢牛のお医者さん
末の子のいちまい守る板歌留多
春立ちぬ (東京)寺澤 朝子
この世佳き松に千両添へて活け
買初やえらびてかろきもの二三
墳墓とは親しきところ冬日影
卵塔の籬の許の竜の玉
野水仙女院とのみの塚一基
墨磨つて窓に見上ぐる寒の月
読み書きに使ふ一と間や日脚伸ぶ
御手洗に浴ぶる雀や春立ちぬ
寒卵 (旭川)平間 純一
一番星凍つればつのる孤独かな
産土の雪の褥の社かな
新年句会あの世この世も賑々し
鏡割社員で祝ふ汁粉餅
霧氷林鉄橋わたる汽笛して
雪原の地平はるかに石狩野
歩みとめ一瞥くるる狐かな
丹精の重さの確と寒卵
冬木立 (宇都宮)星田 一草
鐘の音の神杉を縫ふ淑気かな
父と子の背比べして初鏡
雨あがるほのと紅差す冬木の芽
千本の影をただしく冬木立
竹百幹寒山拾得着ぶくれて
ふるさとの空オリオンの盾かざす
八十八尺平和観音冬うらら
電波塔四肢ふんばつて日脚伸ぶ
|
寒明くる (栃木)柴山 要作
いそいそと謡の妻の初鏡
ぎつくり腰危ふく逃る大くさめ
友の本音やうやくのぞく日向ぼこ
ズームアップの男体女峰深雪晴
鑑真堂守るや真紅の寒椿
手斧飛ばす檜の香り寒四郎
痛きほど頰温きかな寒日和
巨杉叩くけらの谺や寒明くる
出初式 (群馬)篠原 庄治
榛名嶺を隠す出初の水襖
どんど火の明かりにきらりイヤリング
大寒の風柔けれど頰を刺す
雪の襞裳裾に流る浅間山
吹越や命綱巻く電工夫
廃屋の茅葺き屋根の櫛氷柱
登校の子等踏みつぶす霜柱
愚直又よしとし春を待ちにけり
出初式 (浜松)弓場 忠義
去年今年神も仏も灯を入れて
天守へと虹を立たせて出初式
ほんたうの我が顔知らず初鏡
雪平にみどりの滲む七日粥
留守番の餅の膨らむ午後三時
滝凍る一山の音消えにけり
玄関の鍵穴二つ寒に入る
父の背に火種吹きつつ寒の灸
初詣 (東広島)奥田 積
君がゐてこそのこの世や初明り
祓はれて幣さらさらと初詣
町にビル増えしと思ふ初景色
白障子に朝日差しくる淑気かな
初雀二羽来てどつと来たりけり
日の高きにこころ浮かべて初湯かな
湯たんぽを入れてもらひて早寝かな
株分かちし生家のことも寒椿
一水流る (出雲)渡部 美知子
束の間を山襞深く冬日差す
きりきりと霜の声きく出雲かな
寒紅のなほ黙りを通しをり
新しきシャボンの香り女正月
大寒の一水流る神の杜
橋渡りいよよ吹雪の只中へ
鳶鳴けり冬青空を押し広げ
竜の玉記憶の底の子守唄
鷗翔ぶ (出雲)三原 白鴉
一湾を覆ふ寒雲鷗翔ぶ
ごんずいの潜む水槽冬日差す
七種に足らぬ一種買うてをり
一切を闇に返してとんど果つ
凍蝶のためらふごとく翅ひらく
寒の水足して陶工皿を挽く
梅探る許豆の社の二百段
理科室に荷造りテープ春近し
初寝覚 (札幌)奥野 津矢子
罫線を足して文書く冬ぬくし
海難碑尖つてをりぬ冬柏
初鏡しあはせうつるやうに拭く
蓬莱橋渡つてきたり初寝覚
人日や笑うて皺を育てをり
凍道を胸突き坂と思ひけり
水を抜くしばれのこゑを聴く夜かな
雪女郎紺屋の暖簾濡らしをり
動く音 (宇都宮)星 揚子
風邪の子が登校の列見てをりぬ
駄菓子屋の奥に見えたる炬燵かな
寒林を動く音あり動きけり
きつかりと胴衣をまとひ寒稽古
発声の息のまつすぐ寒九かな
裸木のところどころに鳥の影
跳ぬること飛ぶよりも好き寒雀
ページ繰る指先軽き春隣
霜夜 (浜松)阿部 芙美子
頓服の袋を開く霜夜かな
寄鍋や兄弟従姉妹またいとこ
付けつ放しのラジオは落語去年今年
松に来て日差しを返す初鴉
湯治場に蒸す豚まんや深雪晴
料亭の京の雑煮のよそよそし
水仙や硯に水を一二滴
五脚だけのコーヒースタンド日脚伸ぶ
母のこゑ (浜松)佐藤 升子
家々に日の当たりをりお元日
仏壇のちちははに先づ御慶かな
絵馬を吊る紐の緋色もお元日
雑煮椀とほくなりたる母のこゑ
命毛に光をあつめ二日かな
石鹼の泡を太らせ初湯殿
一人食ふ七草粥に舌こがす
散薬に一杯のみづ寒四郎
|