| 最終更新日(Update)'17.01.01 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
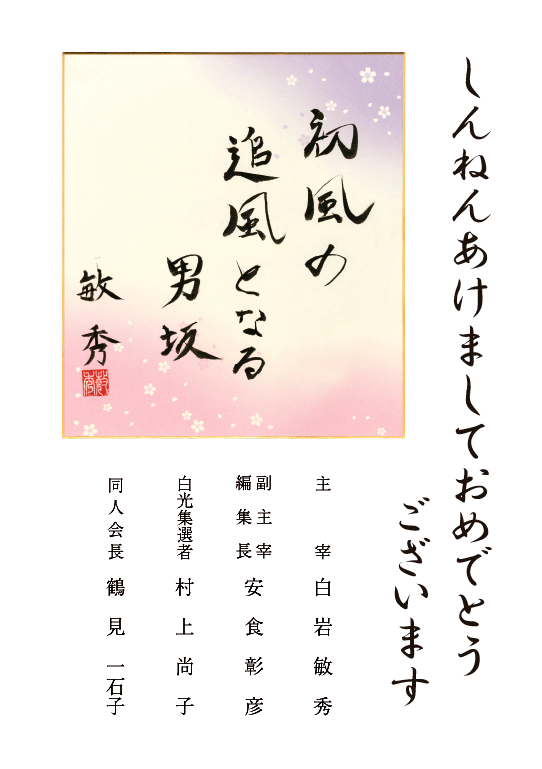 |
|
|
| |
| (アンダーライン文字列をクリックするとその項目にジャンプします。) |
田口 耕 、坂田 吉康 ほか |
佐藤 勲、後藤 政春 ほか |
|
|
|
|
| 季節の一句 |
|
|
| (北 見) 花木 研二 |
|
|
仏壇に灯のともりたる淑気かな 小浜 史都女 山眠るくどに一筋罅走り 渥美 絹代 |
|
|
|
|
|
| 曙 集 | |
| 〔無鑑査同人 作品〕 | |
|
|
|
| 茸 飯 坂本タカ女 その中ののつぽの烏柄杓かな 欄のぬくみにずらり夕蜻蛉 拾ひたる銀杏耳の痒くなる カーテンと玻璃のはざまの秋の蜂 縋るものなく草つかむつるもどき 風呂敷に包みてぬくし茸飯 胡桃落ちつくして刃物供養塚 落葉立ちあがることして吹かれけり 地 蔵 盆 鈴木三都夫 ちまちまと花も終りの浅沙かな 糸とんぼとつて返してゐるばかり 村人も僧も老いたり地蔵盆 地蔵盆一村繋ぐ善の綱 外陣に古りし扁額秋黴雨 簾まだ西日へ残す残暑かな 彼岸花暦違はず咲き揃ふ 草刈女露もて鎌を研ぎにけり 露 草 山根仙花 秋祭りすみたる宮に詣でけり 塵焼いて更けゆく秋を惜しみけり ゆく秋の鐘の音鐘を離れけり 賽打ちし音のことりと秋深む 露草の露のこぼるる程の風 露草や裏戸に残る井戸古ぶ 露草の花に雨降る日となりぬ 雲がゆく雲影がゆく枯野かな 山 眠 る 安食彰彦 稲刈機一集落の稲を刈る さはやかに肩書のなき名刺出し 飛石の上にも秋のなだれをり 柿を剥ぐただただ齢重ねけり あらぬ方見てゐて木莵の鳴いてゐし 恩師逝く嗚呼つひに山眠りけり 竹箸で骨拾ひけり隙間風 葬列がゆく山眠る山めがけ 秋惜しむ 村上尚子 朝市や露にまみるるもの並べ ぶら下がるだけの通草を見て楽し 大原の風に迷へる草の絮 鬼の子に見られ山門くぐりけり 音立ててくる山霧に追ひ越され 行く秋の鞍馬の峠越えにけり 水音やどこ歩きても貴船菊 水占のみづを手に受け秋惜しむ 遺 跡 野 小浜史都女 しろがねの風遺跡野の薄原 蕎麦の風すすきの風も吉野ケ里 遺跡野の風をたひらに蕎麦の花 銅鐸の音澄みきつて野菊晴 聚落に蕎麦と菜畑秋収め 甕棺に炎のあとやそぞろ寒 継ぎはぎの甕棺に秋惜しみけり 環壕の頑丈な柵冬のこゑ |
大願成就 鶴見一石子 孫二人大願成就月満つる 色変へぬ松や侍塚古墳 防空壕は昭和の名残虫のこゑ 機銃掃射うけし板塀桐一葉 手に執りし戦火抜け来し冬帽子 神仏に縋る余生のちやんちやんこ 心の箍弛む晩年冬至くる 歩くことできる幸せ焚火の輪 立 冬 渡邉春枝 通草の実引きて味見の古墳径 露けしや埋葬品の首飾 立冬の日差しとどまる古墳塚 冬に入る溜池に日のさはさはと 葺石の一つ一つに冬日濃し 冬うらら鶏形埴輪の大き口 行き交ふは古代色なる冬の蝶 石蕗咲くや古墳に隣る小学校 をがたまの実 渥美絹代 をがたまの実となる火葬塚の前 掛け替へし杉玉水の澄みにけり 秋日和作りつつ売る桧笠 団栗の落つ芝居小屋解きしあと 穭に穂出たる十坪の神饌田 ゆく秋の風に乗りたる蜘蛛の糸 神の旅目にしむ煙の流れくる 研ぎし刃の青く光れり神の留守 夏のヒロシマ 今井星女 語り部は汗拭はざりドーム前 高々と噴水上げて原爆碑 「皆殺し」とは死語ならず原爆忌 永久に伝へん夏のヒロシマを 俳句大会今日はからずも蛇笏の忌 身に入みて被爆ドームの前に佇つ 秋扇たたみ慰霊碑訪ねけり 資料館見て据りこむ秋深し お母さん 金田野歩女 家苞の南瓜重たくなつてきし 弟切草雨後の湿原満水に 海猫を遊ばせてゐる秋の潮 シンバルの勢ひよろし秋高し 名菊師いつもは優しいお母さん 百舌の晴少し歩を足す散歩道 敵には見えぬ顔菊人形 身仕舞の中途半端や初の雪 一位の実 寺澤朝子 江戸川に棹さす渡し野紺菊 川分れ新川生まる荻の風 人混みの異国語ばかり秋暑し 秋冷の候と書き出す一筆箋 晩年を異郷に姉妹一位の実 乗りつぎの電車夜霧の中を来る 読み耽る先の戦記やそぞろ寒 色葉散る御苑を抜けて丸善へ |
|
|
|
