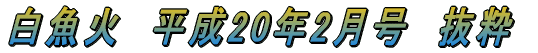| 最終更新日(Update)'08.02.29 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|
| (アンダーライン文字列をクリックするとその項目にジャンプします。) | |
| ・しらをびのうた 栗林こうじ | とびら |
| 5 | |
| 7 | |
| 8 | |
錦織美佐子、横田じゅんこ ほか |
17 |
| 44 | |
| ・白魚火作品月評 鶴見一石子 | 46 |
| ・現代俳句を読む 村上尚子 | 47 |
| ・百花寸評 奥田 積 | 49 |
| ・こみち 「一万歩」 横田美佐子 | 52 |
| ・「白魚火賞」発表 | 54 |
| ・「同人賞」発表 | 58 |
| ・俳誌拝見「原人」 森山暢子 | 63 |
| ・「同人賞」発表 | 64 |
| ・「俳壇」2月号転載 | 68 |
| ・鳥雲集同人特別作品 | 69 |
| 71 | |
| ・今月読んだ本 中山雅史 | 72 |
| ・今月読んだ本 林 浩世 | 73 |
金原敬子、渡辺晴峰 ほか |
74 |
| 122 | |
| ・「白魚火燦燦」ができました。 | 124 |
| ・窓・編集手帳・余滴 | |
|
|
| 季節の一句 |
|
|
| (松江) 富 田 郁 子 |
|
|
| 浅草はいつもお祭り日脚伸ぶ 鈴木三都夫 (平成十九年四月号 鳥雲集) 東京都台東区浅草。三社祭、ほおずき市、羽子板市など一年中お祭がある。しかし掲句は特定の祭ではなく、仲見世や六区興行街のお祭のような賑わいであろう。季節は寒気のまだまだ厳しい一月下旬頃か。いつもの浅草の雑踏の中で作者はふと今までと違ふ夕暮れ時の明るさに気付いたのである。三都夫先生はそこに春の近付いていることを確実に感受されたのである。浅草の固有名詞の働きも大きく、景の中に叙情がある。 汲み置きの水に日脚の伸びにけり 山根仙花 (平成十九年四月号 鳥雲集) 大寒の頃は寒気が最も厳しく、その凍るような感じから「鐘凍つ」「月凍つ」などと言われる。これらは感じであって実際には凍るわけではないが「水道」が凍るのは恐い。そこで用心に水を汲んで置くのである。 昨夜、いくつかの器に汲んでおいた水。その水に作者はふと、日が伸びたなと感じたのである。ふだん、何の気もなく見過ごしてしまう汲み置きの水に、鋭く働く写生の目と、季節の推移に敏感な仙花先生の感受力をすごいと思う。日野草城は 日脚伸ぶいのちも伸びるごとくなり 草城 と詠んだが、仙花先生は寒気の緩んできた日常のよろこびと共に、もうそこまで来ている春に「いのちも伸びる」と感じられたかもしれない。そうであって欲しいと思う。 秋分の頃からだんだん昼が短くなる。短日の続く日々、私はひたすら冬至を待つ。冬至以後は畳の一目ずつ日が長くなっていくと言われているからである。実際には一月半ば頃から日が伸びていることを感ずるのだが。十九年の冬至は十二月二十二日であった。 |
|
|