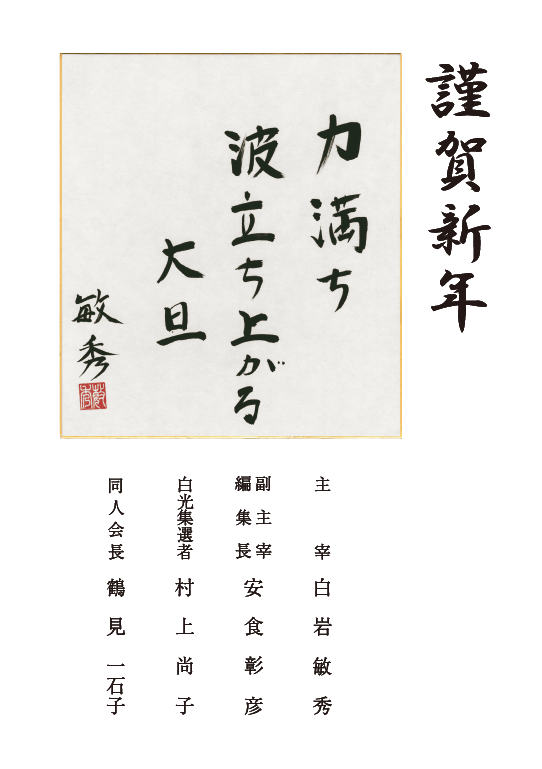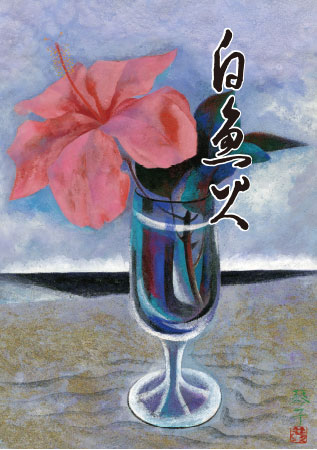十六夜や盆に木目の渦二つ 坂田 吉康(浜 松)
この日の作者は主としての立場なのか、あるいは客としての立場なのかは分からない。いずれにしても目の付け所がユニークである。盆などの塗物は輪島塗のように、何度も漆を塗り重ねたものもあるが、掲句は春慶塗のように透明の漆を塗って、木地そのものを生かしたものであろう。そこに見えていたのが「渦二つ」である。又、季語が十五夜ではつき過ぎ。「十六夜」ならではの余裕から生まれた作品と言えよう。
大会を終へさはやかに師の墓前
この「大会」は鳥取大会のことであろう。作者は行事部の会計として大役を熟された。後日、無事に終わったことを仁尾先生に報告する為「墓前」へ向かった。天気も心の内も「さはやか」そのものであった。
村芝居子供にパパと名指しされ 大河内ひろし(函 館)
「村芝居」は秋の収穫を終えた後、村人が集まってする行事である。出演者は顔馴染みの人ばかりであり、日頃とは全く別の姿が見られるのも楽しみの一つである。ある場面に登場してきたが、白塗りをしたちょんまげ姿の男性だった。客席が騒つくなかで、子供の突然の一声が「パパ」だった。周囲に一層笑いの声が上がったことは間違いない。「村芝居」ならではの光景である。
書き順の迷ふ凸凹秋うらら
何度書いても迷うのは作者だけではない。私も正確な書き順を知らないまま、今に至っている。それを素直に一句に仕立てたのである。今年の秋は短かったが、特別な「秋うらら」の作品となった。
橋見えて村見えてくる蕎麦の花 若林 眞弓(鳥 取)
この句の叙法は、三つの名詞を一つずつ呈示することにより、それぞれの場面を印象付けながら展開させている。最後に見えてきたのが「蕎麦の花」である。日本の典型的な農村風景を、ワイドスクリーンで見ているような鮮やかな作品である。
秋蝶に越され鳳凰堂に入る 石川 寿樹(出 雲)
「鳳凰堂」は平等院の阿弥陀堂のことである。水面に写されたその景は、西方浄土をこの世に出現させたようだとも言われている。そこに表れた「秋蝶」に導かれるように堂内へ入った。作者はしばし、平安の世に思いを馳せたことであろう。
晩秋の橋潜り来る小舟かな 松尾 純子(出 雲)
季語が、初秋、あるいは仲秋だったらどうだろうか。やはり「晩秋」であり、橋を潜ってきたのが「小舟」だったことにより、抒情豊かな作品となったことがよく分かる。声にしてみた時の収まりも良い。
子の声に顔を上げたる蓮根掘 山田ヨシコ(牧之原)
「蓮根掘」は種類にもよるが、正月の需要を控え、寒くなってからが最盛期となる。大変な作業の為、周囲に見向きも出来ないが、突然の子供の声に顔を上げた。子供の声はやはり周囲を元気にする力がある。
棉吹いてより晴天のつづきけり 村松ヒサ子(浜 松)
季語の豊かな言葉に心を惹かれることが多いが、「棉吹く」もその一つ。棉の花が終ると、桃に似たような実ができ、やがてそれがはぜて中から棉が吹き出してくる。〝桃吹く〟〝棉の桃〟などとも言う。「晴天のつづきけり」により、順調に作業が続いたであろうことが窺える。
小銭入れ重し勤労感謝の日 井上 科子(中津川)
〈総身にシャボン勤労感謝の日 仁尾正文〉が、すぐ頭に浮かんだ。この句にはまん中に軽い切れがあるが、内容はいたって分かりやすい。それに比べ掲句は少し難しい。どう解釈するかは自由である。その感覚を養えば、俳句はもっともっと楽しくなる。
秋収めの煙や電車折り返す 小玉みづえ(松 江)
収穫作業のなかでも、特に稲作は秋が節目となる。機械化が進んだ今もその喜びは同じであり、その証徴が田に上がる「煙」である。「電車折り返す」により、この土地の景色を明確に表している。
括られてコスモスぎこちなく揺るる 島 澄江(鹿 沼)
「コスモス」に風はよく似合うが、括ってみるとその趣は全く変わってしまった。自由に風に吹かれている姿こそコスモスに相応しい。「ぎこちなく揺るる」とは実に言い得て妙。
秋茄子を隙間に詰めて荷の届く 河野 幸子(浜 田)
荷造りをしたら少し隙間が出来てしまった。はたと思い付き、畑から「秋茄子」を採ってきて詰めた。親しい間柄であることがよく分かるのが、この句の良さである。
|