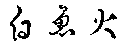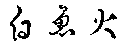大会前々日の夕方、函館空港に集合したのは、むつきさん、実知世さん、くらさん、玲子さんと私の五人。山羽法子さんは名古屋にて合流の予定でした。
大型の台風の余波で不安定な気象でしたが、飛行機は函館から千歳、千歳から名古屋へのルートで飛ぶことが出来ました。
ホテル到着は深夜になりました。
翌日は大変良いお天気になり、元気が湧いて来るようです。
ホテルのロビーで、士別から参加の山羽法子さんが待っていました。これで全員が揃い、一行は六名となりました。
吟行地は熱田神宮、名古屋城、徳川美術館を中心に予定していました。
一番目は熱田神宮ということになり、二台のタクシーに分乗して朝の名古屋を走りました。
熱田神宮の西門に下り立ちました。
鬱蒼とした森の入口と言った感じです。中からは幾種類もの鳥の声が響いています。期せずして朝の参詣です。鳥居に頭を下げて境内に入りました。
境内はひんやりとして、爽やかな空気です。
神域に入りて秋気の引き締まる 広川 くら
時間が早いせいか人影はまばらです。
足元で玉砂利が小さな音をたてます。
長い箒を使って若い男女が参道を清めていました。綺麗になっていく音も印象に残りました。
参道の落葉掃きゆく長箒 広瀬 むつき
「動物でも出て来そうね」と山羽さん。
境内の雑木林は草深く、木立の枝は自由気儘に伸びています。私も狸や狐がこちらを見ているような気がしました。
大木の楠を所々で見掛けました。
その中の一本は注連が巻かれていました。枝も太く伸び、堂々たる姿で立っています。
樹齢千年と知ると、私達は暫くその場から動けなくなりました。千年という悠久の時を経て、今ここに生きていると思うと目眩いを覚えます。
大楠の苔むす幹や秋の雨 内山 実知世
戦国時代、信長の奉納した土塀もすっかり苔に被われていました。森の自然に包まれ時を経ていくのでしょう。
勝運を宿す土塀や椿の実 山羽 法子
宝物殿があり拝見しました。驚いたことは、「古事記」と記した古文書が奥のガラスケースに納めてあったことです。見たことのない漢字ばかりで全く読めませんが。
まだ見足りない思いを残して境内を出ました。
「七里の渡し」は神宮の近隣でした。
人影もなく観光名所という訳でもないようです。ただ五メートルもあるような常夜燈が建っていました。昔の燈台の役を担っていた頃のことを思いました。岸壁が少し迫り出していて、立つと海からの風が強く吹いていました。
水辺に荻の白い穂が揺れて郷愁を誘います。旅人は長い舟路の安全を「熱田さん」熱田神宮に祈ったことでしょう。
桑名まで七里の渡し荻の声 京 子
続いて、「断夫山古墳」に寄りました。
「熱田神宮公園」です。古墳は前方後円墳と聞きましたが、地上に居ては確認することは出来ません。木立の間からこんもりとした丘を確かめるだけでした。空から見たいものです。
断夫山古墳の堀の赤のまま 西川 玲子
再びタクシーに乗り大須観音へ向かいました。観音通りは活気に満ちていました。
何でも揃っているような豊かな名古屋らしい通りでした。名物の鶏カツを昼食としました。名古屋城は午後からになりました。
案内ボランティアの方と一諸に廻ることが出来ました。城の裏話なども面白く話されて感謝を申し上げたいです。
この大会では山羽法子さんが新鋭賞を受けられ仲間として大変嬉しいことでした。
帰りのチケットの関係から大会二日目は早々に帰路につく事になり残念でした。
全国大会特集掲載号を楽しみにしています。
名古屋大会をお世話下さった皆様に厚く御礼申し上げます。有り難うございました。 |