| 最終更新日(Update)'16.01.01 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
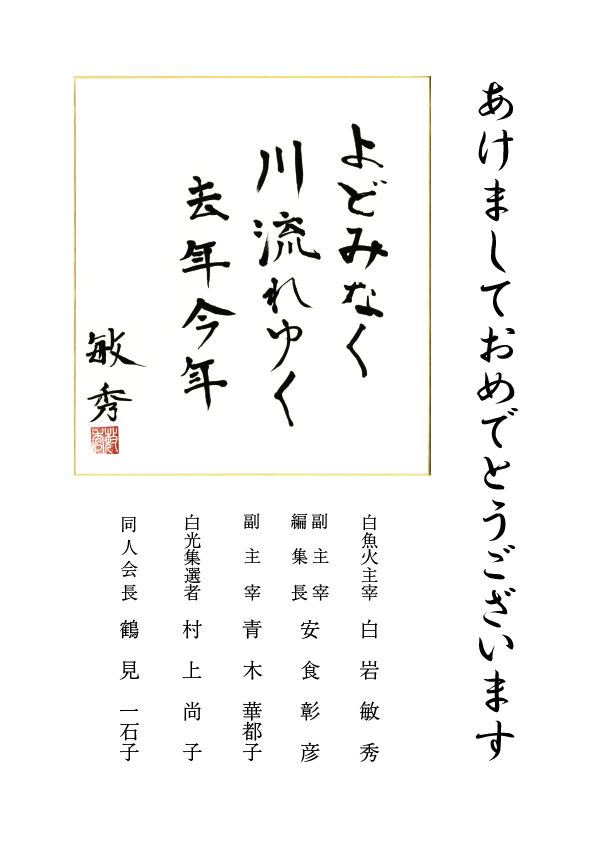 |
|
|
| |
| (アンダーライン文字列をクリックするとその項目にジャンプします。) |
田口 耕 、中山 雅史 ほか |
大隈ひろみ、田口 耕 ほか |
|
|
|
|
| 季節の一句 |
|
|
| (名 張) 檜林 弘一 |
|
|
こざつぱりとして煤逃げの夫帰る 林 浩世 (平成二十七年三月号 白魚火集より) 年末の季題「煤逃げ」は上質なユーモアを含蓄した季題であると思う。掲句は煤逃げをされた?ご主人が帰宅した場面を切取ったものである。そもそも煤逃げはだまって実行するものだが、妻君は急にいなくなったご主人に気付き、多事のなかで怒り心頭であったことであろう。が、煤逃げのご本人はなにやら男前となって(たぶん)床屋から帰宅されたのである。再読すれば、ちょっとした心理のすれ違いや、結果オーライの会話などに想像が膨らむのである。夫婦のコミュニケーションは大切である。 重ね合ふ時計の針や去年今年 牧沢 純江 黒板に文字を大きく初仕事 吉田 美鈴 |
|
|
|
|
|
| 曙 集 | |
| 〔無鑑査同人 作品〕 | |
|
|
|
| 穴 居 跡 坂本タカ女 鉛筆を啣へし句帳雪来るか 酒となる酒蔵の水人の秋 海沿ひの木枯し山の総揺れに 銹まみれなる鯡釜神の留守 昆布を干すずらり船着場の漁船 鮭遡る河口に群るる浜鴉 海に石投げて遊ぶ児昆布乾く 吹雪めく姥百合の種穴居跡 蓮 根 鈴木三都夫 ためらひの色となんこの櫨紅葉 臆病に街路樹遅々と紅葉づれる 風ばかり掬うては伏せ捕虫網 木の実たち落ちて集まりをる処 残る虫ひたすらなれど縷々として もう鴨のゐさうに見えて見当らず と判る高さに通草二つ三つ 掘り出せし蓮根を扱く泥雫 柿 日 和 山根仙花 村中の柿熟れてゐる柿日和 腰下ろす石のぬくみも雁の頃 天高し高しと吊橋ゆらしゆく 流木の湿りに秋の日の滲む 書架の書の傾きしまま秋更くる 抽出にちびし消ゴム秋深し 老いてなほなすこと多し秋晴るる 灯を消せば寒き一間となりにけり 神 迎 安食彰彦 星月夜出雲の国は地で応ふ 妻の影と我が影を守る星月夜 夕食を膝にこぼしてやや寒し 能面の飾られし部屋そぞろ寒 寒北斗地に未盗掘古墳など 足早に素顔の巫女や神迎 宍道湖の波おだやかに神迎 赤ちやんの泣声うれし神迎 夏 帽 子 青木華都子 囀に返す囀学習中 鳥帰る方へと旅をしたきかな 鳥帰る父の帰りを待つ小鳥 五個六個親指ほどの蕗のたう 旅先で買ふつば広の夏帽子 片蔭でいただく仮眠五分ほど 夏帽子目深に一人旅がいい 二泊目は夫と交流木葉木莬 月を待つ 村上尚子 点眼のあとのまばたき秋の空 丼に顔埋め松茸蕎麦すする ひぐらしの声のしみゆく欅かな 少女らの手話よく弾む夕月夜 精進料理食べて句座より月の座へ 廻廊に月浴びてゐる膝頭 境内の闇に月待つ人のこゑ 月光に濡れきし寺の簀子縁 白 秋 忌 小浜史都女 菱の実を売る魚屋の端の端 橋十二くぐる柳川白秋忌 柳川は水より暮るる白秋忌 水郷に笛や太鼓や白秋忌 堀割に万のあかりや白秋忌 水あんどん水路にゆるる白秋忌 白秋忌夜は退屈な四つ手網 小夜しぐれ手を借りて乗るどんこ舟 |
御 成 道 鶴見一石子 津軽富士手よりはみだす林檎摘む 江ノ電の軋み懐かし柿紅葉 無住寺となりて七年新松子 杖ついて菊の薫りを噛みしめり 八十路坂越え生き直す破芭蕉 救急車の音天に去る冬銀河 機を織る仕種語部炉明り 御成道杉落葉踏む音ばかり 中欧の秋 渡邉春枝 雨となる国境までの草紅葉 金秋のモーツアルトの生家訪ふ 家系図はハクスブルグ家秋気澄む 秋雨となるや宮殿コンサート ドナウ川上り下りの星月夜 プラハ城の衛兵交代さはやかに 紅葉かつ散るや古城の石畳 時差呆けのうつろな一日鵙猛る 十 三 夜 渥美絹代 山の日のにはかに暮るる下り簗 木ささげの実の揺れ土蔵かたぶきぬ 埋め戻す遠の遺構や雁渡る 十三夜刺子の針目そろひけり 結ひ直す竹垣木の実よく落つる ゆく秋の茅葺屋根の匂ひかな 返り咲くつつじ木目の浮きし塀 猫死んで家族集まる冬隣 皇居東御苑 今井星女 東京の真ん中にして蝉時雨 門衛と挨拶かはす苑の秋 江戸城の名残を今に松手入 松手入ゆきとどきたる御苑かな 「遠州」の作てふ池の水澄めり 公開の御苑鈴虫鳴くばかり 十五階より眺めたる今日の月 満月に従ふ星のなかりけり 髪 飾 り 金田野歩女 厚物の菊育てをる一クラス 銀杏黄葉の並木楽土を行く想ひ 末枯れの砂洲へ隈なく風渡り 神留守の鄙の社にお賽銭 七五三鹿の子絞りの髪飾り 津軽路の大根洗ふ嫗かな 鴨百羽湖面を捲るやうに翔ち 庖丁の切れ味嬉し菊花蕪 秋 寂 ぶ 寺澤朝子 鵙猛るキャンパスいまはお昼時 古書店の間口一間あきつとぶ 鈴成りといふはこのこと銀杏の実 ことごとくぎんなん踏まれ学生街 安保闘争ありし校塔秋高し 若き日は束の間秋の逝かんとす 黄落す本郷追分一里塚 秋寂ぶや信濃へつづくこの道も |
|
|
|
